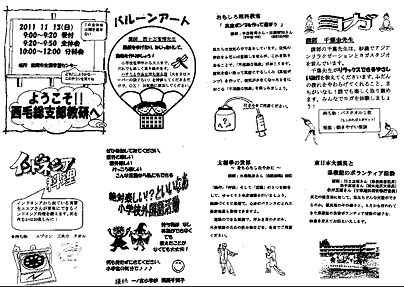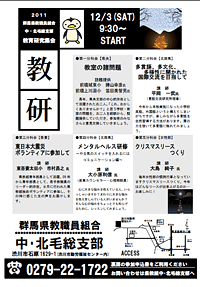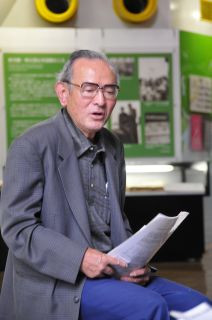また行ってきました。今回は委員会。
「義務教育費国庫負担1/2復元へ」の県議会での請願がどうなるかも決まります。
県議会は年4回。6月、9月、12月、2月。そしてそれぞれに委員会が行われます。
単純に考えると、年4日の委員会で群馬県の教育に関する色々なことが方向付けられたり、決まったり。
10人の委員(議員)さんから色々な質問も出ました。学校関係ばかりではなく、社会教育、文化財、地域のこと・・・。現場の声を聞いたもの、新聞やうわさ、そして個人の思いなど、これで色々な方向づけがなされるのかぁ、と。
学校教育関係では、全国学力テストを悉皆に戻せとか、運動会の日程の件や多忙感解消の件、そして教職員不祥事の件など…。教育委員会も教育長さんをはじめ、次長以下勢揃い、という感じでしょうか?
さて、焦点の義教費の請願ですが、「継続!」と言う声と「採択!」と言う声。継続とは実質的に不採用です。
塚原委員から県教委に質問
「1/2に戻すというのは県の財政にとってプラスなのかどうなのか?」
管理課長
「1/2から1/3になったとき国の交付金は約67億減となった。1/2以下というのは国の責任放棄に近い。県としても1/2のほうがありがたいのは当然」
そして挙手による採決。
採択賛成は 塚原仁委員(リベラル群馬)・角倉邦良委員(リベラル群馬)あべともよ委員(爽風)の3名
継続は 星名建市委員(自由民主党)・中沢丈一委員(自由民主党)・水野俊雄委員(公明党)・桂川孝子委員(自由民主党)・高田勝浩委員(自由民主党)・清水真人委員(自由民主党)の6名
うーん。
政治がどうのではなく、子どもの教育環境や群馬県のことを考えてもらいたいんですけどね。「大人の事情」がかなり大きく働いているようです。
まず、群馬は群馬のことを考え、次にそれらを調整するのは国の仕事なんだから・・・。
文責 長山