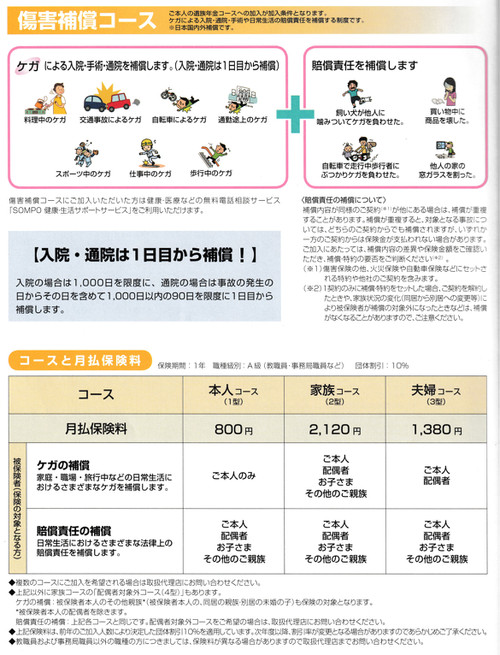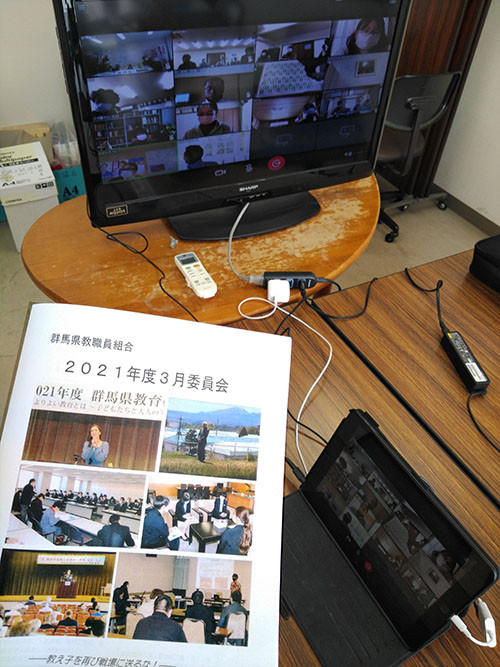2022年4月 6日 (水)
2022年3月31日 (木)
2021年度終了
今日から明日の変化は大きいですね。
異動する肩はもちろん、異動しないとしても1日で違う学校になるわけですからね。
いい気持ちで働ける職場、明日からまたみんなで協力して作っていきましょう!
2022年3月28日 (月)
2022年3月19日 (土)
ヒアリング
昨日は校長先生、全員とヒアリングをしていました。
生徒の話をよく聞くべきであるように、教職員の話もきちんと聞くべきです。「非対象者」はいないのです。さくさく帰ってしまう校長も多いようですが、見習ってもらいたいものです。
が、突然の話、もあったみたいで…。
2022年3月 5日 (土)
2022年2月15日 (火)
スマホ型非接触体温計
各校に導入されますね。
組合交渉でも新型コロナ対策として何らかの施策を、と訴え続け(現実職員室での対策はマスク着用と窓が少し開いているくらい?)、生徒玄関での検温という業務削減の一例としてスマホ型体温計の導入を提案していました。
次は、生徒・教職員の安全のために活用できるよう現場での工夫が大切です!
2022年2月10日 (木)
2022年2月 3日 (木)
2022年1月29日 (土)
全国教育研究集会
全国から様々な実践・研究が発表されます。
面白いです。
官製研修ではないので、色々あるのが面白いです。
ゆえに??なものもあるのですが、色々あるから考えられるなぁ、とも。
夏休みなどに行われる自主的な全国大会も沢山ありますが、様々な方面の実践が一堂に会する、というのでは、貴重ですね。色々選べます。
今年はコロナでリモート開催。基調講演、面白かったです。このくらいの画像は許されるかな?
ただし、一般参加として体験すると、
1)「伝統」が良くも悪くも・・・。
2)逆に毎回新しい参加者ゆえ、毎年同じような議論も。
3)1と2のせめぎ合い。
ま、仲良し集団の研修ではないので、喧々がくがく色々経験することもよいのではないでしょうかね。
全国規模のオンライン会議、難しさもありますが、雑音が入らないのはいいことかもですね(^_^;
2022年1月25日 (火)
役員選挙
本日選挙管理委員会を行いました。告示はこれからですが、
組合ではこんなことをして欲しい!
組合のやり方は気に入らん!
そんな方はぜひ立候補を検討してください!!
誰のためでもない、自分たちで作る自分たちの活動。
現場の色々な声を生かすため、遠慮せずにどうぞ(^_^)
最近の記事
こちらもどうぞ
携帯URL
更新ブログ
|