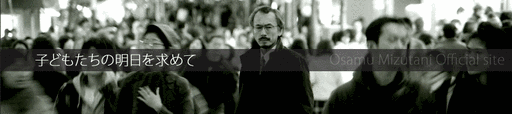日教組と言えば「こんな事に反応するでしょ」と、どちらの方からも期待があるようなのですが、すみません、メインとして取り扱っていませんで・・・。しかし、別の話題もあったり、別の角度からの見方が気になったり、と言うことでブログ記事としてみます。
はだしのゲン「描写過激」…小中に閲覧制限要請 (朝日記事 読売記事)
ありゃりゃ。「市民から撤去を求める声」だそうで、まぁ撤去を求める声も、開架を求める声もあるわけですけどね。
「別の話題」とは、(日付が変わってしまったので)昨日googleが
「Google では、本日、広島平和記念資料館と長崎原爆資料館と協力し、両資料館が所蔵する原爆に関する歴史的資料を「Google 歴史アーカイブ」で公開します。」
と発表したことで、日本の歴史アーカイブ第1号が広島・長崎の原爆資料館というのもあり、この時期色々考えることは大切かなと考えます。
まぁ、開架反対派の方が問題にしていたのは原爆の方ではなく別の点でしょうけれど…。この際なので、自分が気になったのはこの記事が大枠訴えようとしていることに近いです。
「はだしのゲン」問題からみえる日本の教育 前屋 毅
我々公務員は支持命令系統がきちんと整うべきで、現場の判断であれこれやられたらたまったものではない、のかもしれません。
文科省でしっかり考えたことをきちんとやってもらわなければ何が日本の公教育だ、ということでしょう。
しかし、
教職員も「優秀な行政公務員」であるべきなのか?
深く考えれば考えるほど答えが出ません。
もうここまで書いたら、乗りかかった船、と言うことで、
「はだしのゲン」のアニメを、8月31日までGyaO!が無料配信
Web漫画「原爆に遭った少女の話」が話題 祖母の体験を孫が描いて公開
そう言えば以前「はだしのゲン」の作者中沢啓治さん、太田支部の事務所に入らしたこともありましたね(と言っても自分は写真で見ただけですが)。
さて、ご期待に沿える「日教組的」な話題だったでしょうか?
いわゆる炎上ネタですかね?
文責 長山